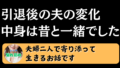私は明美。59歳で近所のスーパーでパートをしている。
還暦を迎えるまであと数ヶ月となったある日のこと。私はふと過去のことを思い出していた。気づけば、31年という長い時間を夫と共に過ごしてきた。二人で歩んできた道のりは、平坦ではなかったが、それでもここまで何とかやってきたのだ。しかし思い返すと今でも胸がざわつく出来事がひとつ。
それは10年前にまで遡る。私がまだフルタイムで働いていた頃の話だ。あの頃、私は今のようにパートではなく、社員として働いていた。仕事は忙しかったが、それでも充実していて、同僚たちと助け合いながら日々を乗り越えていた。しかし、突然の人手不足により私は他の部署の応援に行くことになった。期間はおよそ2ヶ月。しかも単身赴任だ。夫も快く送り出してくれたし、私はその仕事を受けることにした。
応援先の部署には、剛という男性社員がいた。私よりも年下で、明るくて、いつも誰かに気配りをしているような人だった。最初は特に何も感じていなかったけれど、仕事をしていくうちに、剛が頻繁に私に声をかけてくるようになった。仕事の相談から始まり、次第に雑談へと広がり、いつの間にかプライベートな話まで持ちかけてくるようになった。
ある日、仕事が終わった後、剛に食事に誘われたことがある。何気なく応じて、二人で近くの居酒屋に行った。お酒も進み、リラックスした雰囲気の中で、彼は突然こう言った。「実は、前から明美さんのことが気になっていました」と。「はい?」その言葉に驚きつつも、まさかと思った。自分が誰かに想われるなんて、もう随分昔の話だと思っていたからだ。私は冗談だろうと笑って返したが、彼の眼差しは真剣だった。
「ありがとう。でも、私は結婚しているし、夫もいるの。好きって気持ちは嬉しいけど剛くんと良い関係になるのは無理よ」と、当たり前のように断った。けれども、剛はそれで引き下がらなかった。「俺は諦めませんよ?しつこい男ですから」「いや現実的に考えて無理だからね」その後も仕事の合間に何度か告白してきた。「ただ一度でいいから、二人でちゃんと話がしたい」と、懇願するように言われた時、私は心が揺らいだのかもしれない。
応援期間も残り少なくなったある日のこと。お酒のせいにしたくはないのだが、それもあったと思う。二人でいつものようにお酒を飲みに行って、私も単身赴任だったから寂しかったのだと思う。その寂しさを剛で埋めるかのように、私は彼と一線を越えてしまったのだ。正直、そのときのことはあまり鮮明には覚えていない。自分でも信じられないくらい、ぼんやりとした感覚だった。ただ、「もう一度だけ、あなたに会いたい」と彼が言ったこと、その言葉が胸に残っていたことは覚えている。
それでも、私は元の部署に戻り、何事もなかったように日々の生活に戻った。夫との関係は以前と変わらず、剛とのことは夢のように感じられた。浮気が実ることなんて、最初からないのだと自分に言い聞かせていた。それに、夫と一緒にいるのが私の普通で、そこから離れる勇気などなかったのだ。剛とは自然に距離ができて、いつの間にか彼の存在も遠くに感じるようになった。あの2ヶ月は、私にとってほんの一瞬の、消えてしまいたくなるような甘い時間だった。
あれから10年。そんな過去を持つ私が、今また過去を振り返っているのは、夫との結婚生活にマンネリを感じているからだろうか。あの時剛と過ごした数日間が、心の片隅に小さな後悔を残しているのと同じように、今の生活にもどこか物足りなさを感じる自分がいる。でも、それは誰にも言えない秘密のまま、これからも私の胸の奥にしまい続けるのだろう。
還暦を迎えるまであとわずかという時期。夫の様子に少しずつ変化が現れ始めた。長年一緒に暮らしてきたからこそ、小さな違和感にも敏感になる。普段は仕事から帰ると、テレビを見ながらぼんやりと過ごしていたはずの夫が、最近は妙に帰りが遅くなる日が増えた。スマホをこそこそと操作する姿も目に付く。最初は気のせいかと思っていたのだが、どうやらそうではなさそうだと確信するようになった。
ある日、夫のシャツの襟に見慣れないリップの跡を見つけた。そんなに目立つものではなかったが、私にははっきりとそれが浮気の証拠だと分かった。心の中で疑念が膨らみ、それはもう抑えきれないほど大きくなっていた。問い詰めても、夫は「何でもない」の一点張りで、本心を明かそうとはしない。だけど、私には感じ取れる。これは、かつて私が剛に惹かれたときと同じような、相手に心が向いているときの振る舞いだと。
それからしばらくして、ついに夫の浮気の証拠を掴んだ。相手は会社の後輩の若い女性だった。出張という名目で、実は彼女と一緒に過ごしていたことが分かり、私は愕然とした。あれほど誠実で優しかったはずの夫が、私の知らないところで、そんなことをしていたなんて。だけど、同時に不思議と冷静な自分もいた。夫に対して感じた失望よりも、どこかで「やっぱり」と納得している自分がいたのだ。結局私たちは似た者夫婦だったのかもしれない。互いに裏切り裏切られている。私も夫のことは責められない。
せめて嫌いにならぬよう還暦を迎える前に、私たちは離婚することを決めた。夫との31年の結婚生活に突然幕が下りる。その決断に至るまでには、悲しみや怒り、いろんな感情が渦巻いていたが、最後にはただ静かな諦めが残った。結婚生活を終えることが、きっとお互いのためだろうと、そう思うしかなかったのだ。
離婚が正式に決まり、一人きりになった私は、ぽっかりと心に穴が開いたような感覚に襲われた。新しい生活を始めなければいけないというのに、どうしたらいいのか分からず、ただ毎日をぼんやりと過ごしていた。そんなある日、ふと昔の仲間たちとよく通っていた飲み屋を思い出し、ひとりでふらりと足を運んでみた。
その店に入ったとき、まさかの再会が待っていたのだ。カウンター席に座っていたのは、剛だった。10年前のあの短い時間が頭をよぎり、一瞬言葉を失った。でも、彼もすぐに私に気づいて、驚いたように目を丸くした。「明美さん…久しぶりですね」と、懐かしい笑顔で声をかけてくれた。彼も変わっていない。少し歳を重ねたようには見えるけれど、相変わらずの明るい笑顔がそこにあった。
私たちは自然と話し始め、近況を語り合った。話を聞くと、剛も2年前に離婚を経験していたという。「バツイチ仲間ですね」と笑い合いながら、久しぶりに心の底からほっとしたような気持ちになった。お互いにそれぞれの人生を歩んできて、そして今、こうしてまた偶然に巡り合うなんて、まるで不思議な運命に導かれているような気さえした。
剛は、離婚してから一人で過ごすことの寂しさを語り、私も最近の出来事を打ち明けた。夫の浮気、離婚のこと、そしてこれからどう生きていこうかと途方に暮れている自分の気持ちを話すと、剛は優しく頷きながら聞いてくれた。言葉少なに、ただ「分かりますよ」と言ってくれたその言葉が、胸に染み渡った。
いつの間にか、店を出た私たちは夜の街を一緒に歩いていた。特に行き先を決めていたわけではない。ただ、隣に剛がいることが心地よくて、その時間がずっと続けばいいとさえ思った。過去のことを全部消し去ることはできないけれど、今この瞬間に剛といることで、ほんの少しだけでも救われている自分がいると感じた。
夜風が少し冷たく感じる季節になっていた。剛が「今日は一緒にいましょうか」と言ったとき、私はためらうことなく頷いた。「えぇ…朝までお願い…」「了解です」10年前には叶わなかった、あの約束が今、ようやく果たされたような気がしていた。私たちは夜の街に溶け込むように、静かに消えていった…