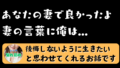私の名前は美津子で、65歳の主婦です。もう2年間、夫の面倒を見ています。夫は70歳。年相応に見えますが、心の中ではどんどん過去に戻っていっているような気がします。毎日、何度も同じ質問をされることがあり、時には突然怒り出すこともあります。昔の夫はそんな人ではありませんでした。結婚して40年以上、ずっと穏やかで、家族思いの優しい人だったのです。
息子たちが時々孫を連れて訪れてくれるのが、私にとって数少ない楽しみです。けれど、夫はその孫の名前を忘れてしまうことが増えてきました。息子の名前は覚えていますが、その息子の子どもたちの名前までは、どうやら頭に入っていないようです。ある日、家族が揃って団らんしているとき、夫が孫の名前を間違えて呼び、皆の前で黙り込んでしまったことがありました。その時の彼の寂しそうな表情を思い出すと、今でも胸が痛みます。
それだけではありません。夫は時々、家の中で見知らぬ場所にいるように見えるのです。リビングに座っているのに、「ここはどこだ?」と不安そうに聞いてくることもあります。そんな風に、少しずつ夫は目の前の現実を手放しているのだと感じます。
毎日、夫の面倒を見ていると、気が滅入ることも多いです。私の話にまともに応じることは少なく、何度も同じことを繰り返しては謝る夫に、私は苛立ちを感じてしまう自分が嫌になります。それでも、私は彼の妻だからと自分に言い聞かせ、なんとか毎日を過ごしています。けれど、良くなることは決してなく、悪くなることばかりが続くのだとわかっていると、次第に疲れ切ってしまっているのが現状です。
そんなある日、夫を預けている施設に彼を迎えに行きました。その日も日課のように、顔を見せて一緒に帰るつもりだったのですが、施設の庭で夫が見知らぬ女性と親しげに話しているのを見つけました。私は驚いて足を止めました。夫があんなに楽しそうに笑っているのを、もう何年も見ていなかったからです。彼の隣には、若作りのピンク色のセーターを着た女性がいました。その人が桃子でした。
「美津子さん、こんにちは。」
彼女は笑顔で私に声をかけてきました。桃子は、自分の親をこの施設に預けているので、たまたま私の夫と出会ったのだと言いました。それだけなら、私も少し安心できたでしょう。だが、夫が彼女に向けていた視線は、昔の私に向けてくれていたような、あの優しい眼差しそのものでした。そして、彼が私に言った言葉が、私の心を深く傷つけました。
「もう、帰る時間よ。さあ、行きましょう。」と、私はいつも通りに夫に声をかけました。
だが、夫は首を横に振って、「いや、俺は帰らないよ。だって、俺の奥さんはここにいるんだ」と言い張ったのです。夫は桃子の方に指をさして、笑いながら「俺は一途だからね。あんたは誰なんだ?」と私に向かって言いました。
「あなた、何を言ってるの?私は美津子よ、あなたの妻の…!」そう言っても、夫は私のことをただ不思議そうに見つめるだけでした。「いや、俺の妻は桃子だよ。」と繰り返すばかりです。何なんだこの男は…。一体誰が面倒を見てると思っているのか…。私は、彼をどうしたら家に連れて帰れるのか、途方に暮れてしまいました。その時でした。桃子が私に向かって、柔らかい声で言いました。「ねえ、美津子さん。それならしばらく夫を交換をしてみない?」あまりにも唐突な提案に、私は呆然としてしまいました。何を言っているのか、彼女の言葉が頭に入ってきませんでした。「交換って…何を考えているの?」と私は問い返しました。彼女は、まるで私を気遣うように微笑んで、「もし、美津子さんがご主人の面倒を見るのが辛いのなら、少しの間だけ私が代わりますよ。たまには楽してみませんか?」と説明してきました。私は最初、断固としてその提案を拒否しました。そんなことをして、何になるのかと。でも、何度も帰ろうと促しても、夫は私の手を握ろうとせず、代わりに桃子の手をしっかりと握っている。その姿を見て、私はふと心が折れました。「いいわ…」と小さく答え、夫を施設に残して帰る決意をしました。その後、私は桃子が迎えに来た彼女の夫、健大さんと一緒に帰宅することになりました。健大さんは、長身で落ち着いた雰囲気の男性でしたが、車の中で何度も私に謝罪を繰り返しました。「妻が本当に申し訳ない…」その言葉が、逆に私を複雑な気持ちにさせました。
彼が謝る理由なんてないのに、彼の真摯な態度に少しだけ救われた気がしました。私は「謝らなくていいんです」と何度も言いました。健大さんが悪いわけではないし、責任感の強い彼が一生懸命に謝ってくる姿に、むしろ不思議な安心感さえ覚えました。
健大さんは穏やかで話しやすい人でした。朝食の席で、「何かお好きなものはありますか?」と尋ねてくれたり、私が気を使わないようにと常に心を砕いてくれていました。そんな彼と過ごすうちに、私は気づけば心が少しずつ軽くなっていくのを感じていました。
考えてみれば、ここ何年もずっと夫の介護をし続けて、心の底から休むことなんてありませんでした。健大さんとの生活は、私にとって初めての「休息」を感じさせるものだったのです。夫といるときには、常に緊張していました。次にどんな症状が出るか、何を言われるか、心配ばかりで安らぐ暇などなかったからです。
ある夜、夕食を一緒にとっていると、健大さんがぽつりとこんなことを言いました。「美津子さん、あまり無理をしないでくださいね。あなたがどれだけ大変だったか、なんとなく分かる気がします。」その言葉に、私は涙が溢れて止まりませんでした。誰にも理解されていないと思っていた自分の辛さを、彼が分かってくれた気がして、心がふっと軽くなったのです。
私たちは、自然と一緒にいる時間が増えていきました。最初はぎこちなかったけれど、次第に互いの話をするようになり、時折冗談を言って笑い合うこともありました。健大さんの優しさに触れ、私は気づけばその時間を楽しむようになっていました。
そして、そんな穏やかな日々の中で、私はついに一線を越えてしまいました。ある夜、健大さんが私の手を取って「今までお疲れさま」と静かに言った時、私は感情が抑えきれなくなり、彼に寄りかかるように抱きついてしまったのです。そのまま、私たちは言葉もなく一晩を過ごしました。
その翌朝、私は恐ろしい罪悪感に襲われました。夫がまだ生きているのに、私は何をしているのかと、自分を責める思いが頭をよぎりました。でも、健大さんそんな私に優しく微笑み、「そんな風に自分を責めなくてもいいんですよ」と言いました。
「どうして?」と私は問い返しました。すると健大さんは、ゆっくりと話し始めました。「実は…桃子は以前、あなたのご主人と関係を持っていたんです。」
私は信じられませんでした。夫がそんなことをするはずがない、と反射的に否定しましたが、彼の話は続きました。「でも、彼の症状が進むにつれて、約束を守らなくなったり、浮気相手の名前すら忘れてしまった。だから、その関係は自然消滅していったんです。でも桃子は、それが我慢できなかったんでしょうね。だからまた、彼に近づいたんです。」
健大さんの言葉に、私は言葉を失いました。夫が他の女性と…浮気をしていたなんて、そんなこと想像もしていませんでした。でも、もしそれが本当なら、桃子があんなに親しげに夫と接している理由も理解できます。そして今、彼女は再び夫と接触し、あたかも夫婦であるかのように振る舞っているのです。
ショックと同時に、私はひどく疲れている自分に気づきました。夫に仕えること、認知症の症状に振り回される日々に、もう限界だったのかもしれません。健大さんが語った言葉のすべてが、私の中にあった苦しさや怒りを揺り動かし、私はとうとう彼に言いました。
「私、もう良いかな。健大さん、もしあなたがよければ、私たち一緒に生きていきませんか?」その言葉は、自分でも驚くほど自然に口をついて出ました。
健大さんはしばらく黙っていましたが、ゆっくりと頷きました。
それから、私たちは共に離婚して新しい生活を始めることになりました。もちろん、夫と桃子のことが完全に消えるわけではありませんでした。桃子は、時折施設で夫と過ごしている様子が見えましたが、それが本当の愛情なのか、それとも単なる執着なのかは分かりません。夫もまた、時折桃子の名前を呼んで、施設のスタッフを困らせていると聞きました。こんな夫といるのは彼女の意地なのでしょうか…。
そうして奇妙な夫婦交換のような関係は続いていますが、私と健大さんは少しずつ新しい日常を築いていきました。私たちは互いに気遣いながら、穏やかに暮らしています。夫への罪悪感は、まだ完全には消えないけれど、それでも私は今、少しずつ心の平穏を取り戻しています。夫と桃子がどうなろうと、もう私はそのことに深く関わるつもりはありません。疲れ切っていた私にとって、健大と一緒にいることでようやく得られた休息と、互いを支え合う安らぎが何よりも大切だからです。