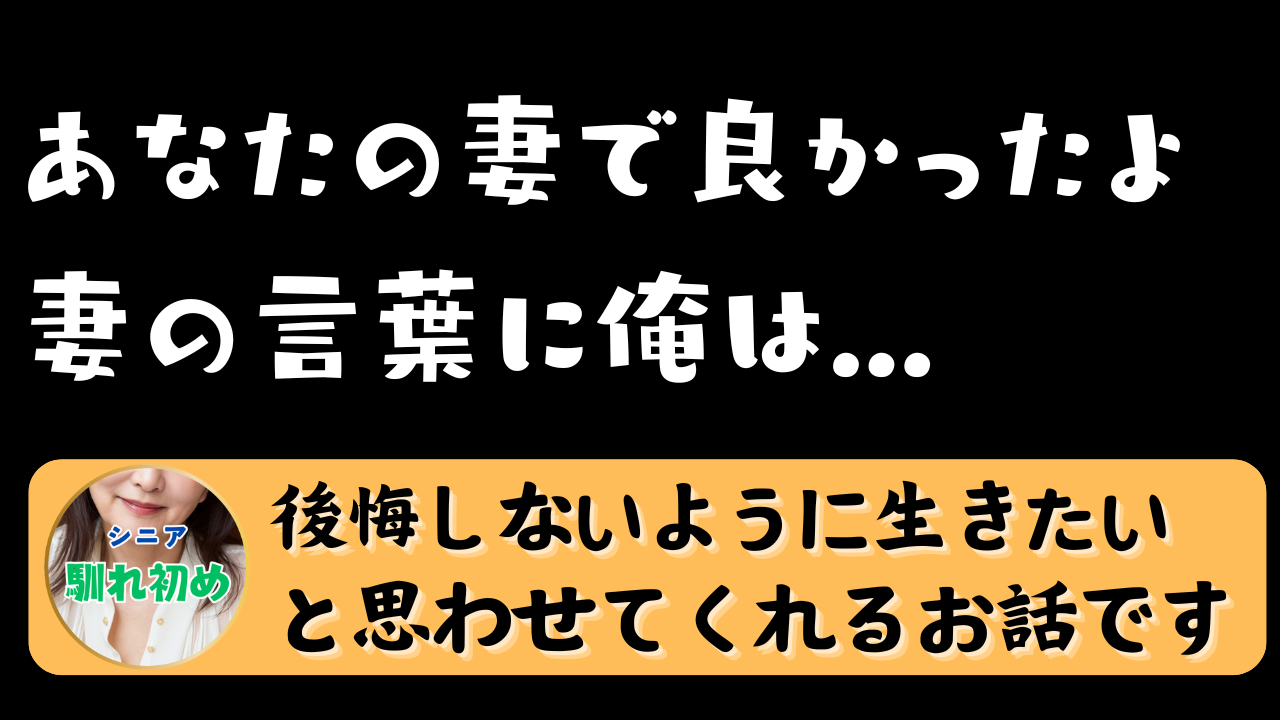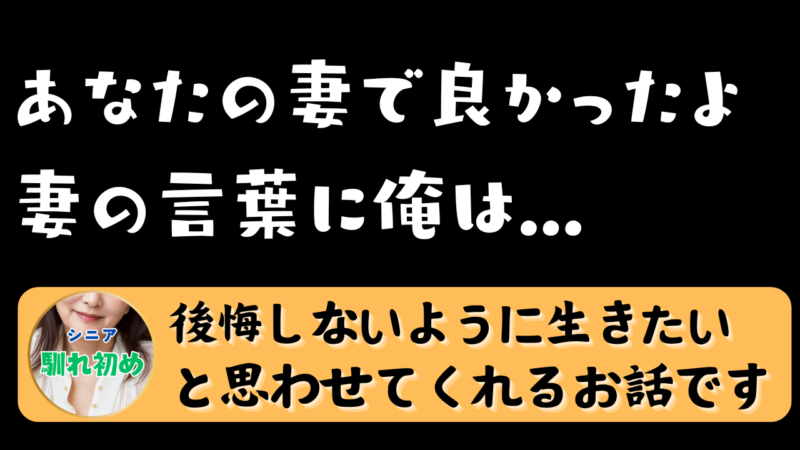
私の名前は高志、65歳です。最近病院の待合室の椅子に座り、ぼんやりと窓の外を見ることが増えたように思います。実は数ヶ月前から、ほとんど毎日のようにここへ来る生活が続いています。妻の久美子が倒れてからというもの、彼女の面会に通う日々が始まりました。
あの日、久美子が倒れたときは、まさかこんなことになるとは思いもしませんでした。顔色が悪く、普段とは違う様子に不安を覚えながらも、大したことはないだろうと高をくくっていたのです。しかし、病院での検査の結果、彼女は末期のすい臓がんと診断されました。医師から「もう治療の選択肢はあまり多くありません」と告げられ、目の前が真っ暗になったのを覚えています。余命は、残りわずかだと聞かされました。
それ以来、毎日こうして病院へ通っています。でも、それまでの私たち夫婦の関係は決して良いものではありませんでした。長年連れ添ったこともあり、日々の生活の中で小さな不満が積み重なって、口論になることが増えていました。例えば、些細なことで言い争いをすることもありました。買い物の帰り道で、買ってきた野菜が違うと久美子が文句を言えば、私もつい「そんなに細かいこと気にしなくていいだろう」と言い返してしまう。お互いに譲らず、しばらく無言のまま家に帰ることも少なくありませんでした。
家事についてもよく口論になりました。久美子が「食器をちゃんと洗っておいて」と頼むのに、私はついテレビに夢中になって忘れてしまう。そうすると、帰宅した久美子がイライラして「またちゃんとやってくれてない」と怒るのです。私も腹を立てて、「そんなに神経質にしなくてもいいだろう」と声を荒げる。そんなやり取りが続くうちに、私たちの間にいつの間にか溝ができていたのだと思います。
そんな風にして、言い争いが続く毎日でしたが、倒れてからの久美子は変わってしまいました。病室のベッドに横たわる彼女は、以前のように活気がなく、静かで、時折痛みに堪えるように顔をしかめます。その姿を見るたびに、私は心が締め付けられるような思いがします。「もっと優しくしてやればよかった」──これまでの自分の言動がどれだけ彼女を傷つけていたか、今になって痛感しています。小さなことで腹を立てて、彼女をないがしろにしていた自分が情けなく、後悔の念に苛まれるばかりです。
病室に入ると、久美子は穏やかに微笑んでいました。以前の険のある表情は消え、どこか儚げな雰囲気を漂わせています。その笑顔を見るたびに、胸が締め付けられるようでした。医師に容態を聞くたびに、良くない話ばかりが続きます。「痛み止めを使っても限界があります」「体力がどんどん落ちている」──そんな言葉を聞きながら、私はただ頷くだけです。何もできない自分がもどかしく、悔しい思いでいっぱいです。
病室での時間は、とても静かです。久美子が静かに寝息を立てているのを見つめる時間が、私の日常の一部になってしまいました。目を閉じて眠る彼女の姿を見ていると、ふと、彼女がいなくなった後のことを考えてしまいます。その度に、胸が締め付けられるような不安が押し寄せてくるのです。「もし、久美子が本当にいなくなってしまったら……」そう考えると、耐え難い恐怖が私を襲います。
そんな私とは対照的に久美子は、どんなに辛くても弱音を吐かない人でした。病気が発覚してからも、「私は大丈夫よ」と言い続けていました。でも、その言葉が嘘だということくらい、私には分かっています。今さらになって、もっと彼女の言葉に耳を傾けていればと、悔しさが募ります。もしかしたら、彼女はもっと前から苦しんでいたのかもしれません。私はそのことに気づかず、ただ自分のことで精一杯だったのです。
病室の外から、窓を通して沈みゆく夕陽が見えます。その美しいオレンジ色の光が、彼女の顔を柔らかく照らしていました。私はその光景を、まるで時間が止まっているかのように見つめていました。この瞬間が永遠に続けばいいのにと、そう願わずにはいられませんでした。でも、時間は残酷なほどに確実に進んでいます。彼女が私のそばからいなくなるかもしれない現実が、少しずつ迫ってきているのです。
久美子の手を握りしめながら、私は心の中で繰り返し祈りました。
「どうか…もう少しだけでも良いから、彼女を元気にしてあげてください」と。
久美子の病室に足を運ぶ日々が続いています。医師からの言葉に少しでも希望があればと願いながら、私はただただ彼女の回復を祈っていました。しかし、現実は厳しく、彼女の体調が良くなる兆しは見られませんでした。それでも私は、少しでも良い治療法が見つかるかもしれないと、その可能性にすがりついていました。
病室のドアを開けると、久美子が静かにベッドに横たわっていました。今日はいつもよりも顔色が良く、私を見ると微かに微笑んでくれました。そんな久美子の表情を見るだけで、私は少しだけ安心できるのです。でも、その笑顔の裏に隠された痛みと不安が分かるからこそ、胸が痛みました。毎日顔を見に来るたびに、彼女の辛そうな姿を見るのが心苦しく、何もできない自分の無力さに打ちのめされる思いでした。
ある日、いつもよりも久美子の状態が良いと聞かされ、少しほっとしました。久しぶりに彼女と会話ができるかもしれない、そんな期待を胸に病室へ入りました。彼女はいつもより目がしっかりと開いていて、穏やかな笑顔を浮かべていました。「今日も来てくれてありがとうね」と、いつもよりも元気そうな声で言ってくれました。その声に、私は少しだけ安心し、ベッドのそばに座り込みました。
「どうだ、体調は?」と尋ねると、久美子は小さく頷き、「今日は少し楽なの」と答えました。久しぶりにこうして普通に話ができることが嬉しくて、つい「それはよかった」と声を弾ませてしまいました。すると、久美子は少し寂しそうな表情を浮かべて、ふと窓の外に目を向けました。
「ねえ、あなた…少し話がしたいの」彼女がそう言うのは、これまであまりなかったことです。久美子のその言葉に、私はなんとなく胸騒ぎを感じました。何か特別なことを話そうとしているのかもしれない、そんな予感がしたのです。
「私、最近いろいろ考えてたの。こうして病気になって、体が思うように動かないと、自然と昔のことを思い出すのね」と、久美子は穏やかな声で話し始めました。「私たち、いろいろあったけど、こうして今まで一緒にいられて、本当に良かったと思うの。あなたと結婚して、幸せだったよ」
その言葉に、私は何と言っていいのか分からず、ただ黙って聞いていました。胸の奥がじんと熱くなり、目の奥が熱くなるのを感じました。久美子はまるで、自分の最期を悟っているかのように、静かに、そして丁寧に言葉を紡いでいました。
「あなたには、たくさん迷惑をかけたと思うの。気が強くて、細かいことばかり気にして…いつも怒ってばかりだったよね。でも、そんな私にずっと付き合ってくれて、本当にありがとう」彼女の声はだんだんと弱くなり、言葉を紡ぐたびに小さなため息をつくようでした。
「いや、俺の方こそ…もっと優しくしてやればよかったんだ。お前が頑張ってるのを知ってたのに、俺は自分のことばかりで…」言葉が震えているのが、自分でも分かりました。久美子に言われるまでもなく、私はこの数ヶ月間ずっと後悔していたのです。もっと彼女を大切にしていれば、もっとたくさん笑顔にしてやれたはずだと。
久美子はかすかに首を振って、「そんなことないわ。私は本当に、あなたの妻で良かったと思ってるの」と優しく言いました。「一緒にご飯を食べて、買い物して、些細なことで揉めたけど…それが私には幸せだったの。どんなに言い争っても、あなたがそばにいてくれた。それだけで良かった」
「そんなこと言うなよ…まだこれからもずっと一緒にいるだろう?」私は懸命に笑おうとしましたが、言葉を言い終える頃には声が詰まり、涙がこぼれそうになっていました。久美子は、私の手をぎゅっと握りしめ、「ありがとう、これまでずっとそばにいてくれて…あなたの妻でいられて、本当に幸せだった」と小さな声で言いました。
「あなたの妻で良かった…ありがとう」その言葉が、彼女の最後の言葉でした。私は彼女がもう話せなくなることを知りながら、ただ彼女の手を強く握りしめることしかできませんでした。
それから間もなく、久美子は静かに息を引き取りました。その瞬間、私の中の時間が止まったような感覚に陥りました。あまりに静かで、あまりにあっけなくて、何が起こったのか理解できません。でも、久美子の冷たい手を握ったとき、彼女が本当に私のもとを去ってしまったのだと、ようやく実感しました。
久美子がいなくなった日々は、想像していた以上に辛く、寂しいものでした。家に帰っても、そこにはもう彼女がいません。静まり返った部屋に、一人でいる時間が増えました。何をしていても、ふと久美子のことを思い出し、胸が締め付けられるような気持ちになるのです。
それでも、私は久美子が最後に見せてくれたあの優しい笑顔を思い出すたびに、前を向こうと思うようになりました。残された家族、娘や孫が私のそばにいてくれます。彼らのために、まだやるべきことがあると、そう思うようにしています。久美子が私に教えてくれたのは、どんなに辛いことがあっても、日常の中に幸せはあるということです。
久美子の遺影に向かって、「ありがとう」と心の中でそっとつぶやきながら、私は今日もまた、彼女の分まで元気に過ごそうと思っています。
きっと久美子は見てくれていると思うから…