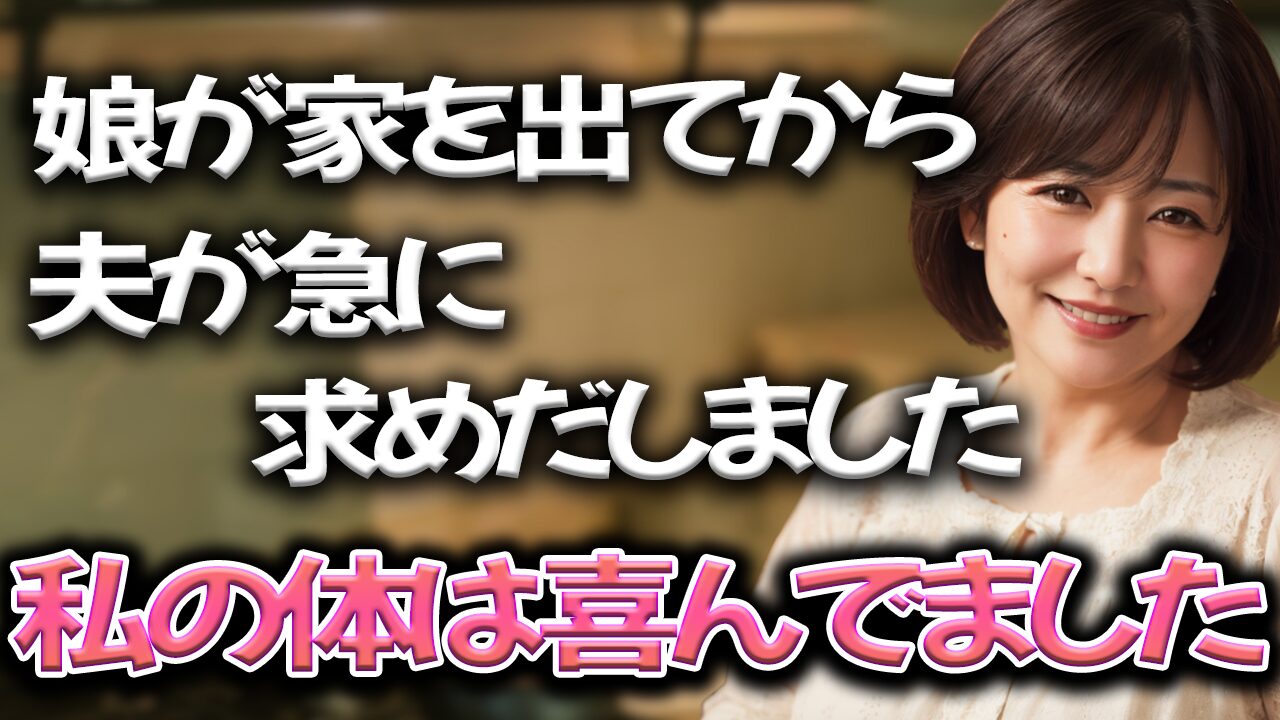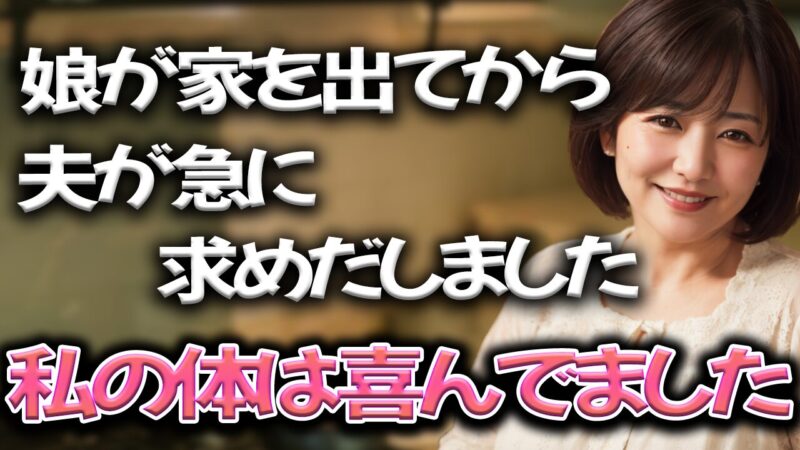
彼の手が、そっと私の胸に触れたとき、私は思わず息が止まりました。もう長いこと、触られていなかった場所。なのに、まるで昨日まで恋人だったかのように、私の身体は覚えていました。浴衣の合わせ目から夫の手が滑り込んできて、私は自分でも驚くほど、ブルブルッと背中を震わせてしまいました。
この歳になって、こんなふうに触れられることに身体が反応するなんて。恥ずかしいような、でもどこか嬉しいような、そんな気持ちがごちゃまぜになって、私はただ、身を任せるだけでした。
夫の博は、黙ったまま、私の肩に唇を落としました。そのぬくもりが、ゆっくりと首筋をなぞっていくたび、私はなすすべもなく彼に身を預けていました。髪をかき上げる手も、胸元をやさしく包み込む手も、すべてが丁寧で、まるで壊れ物を扱うようでした。ああ、こんなふうにされたのは、いったい何年ぶりだったでしょうか──。
私の手は、彼の背中にそっと添えられていました。求められていることが、ただただ嬉しくて、何も言えなくなってしまったのです。胸の奥から、じんわりと熱が湧いてきて、やがてそれは腹の奥から伝わっていきました。自分でもこんな感覚がまだ残っていたことに驚きながらも、それでも、どこか懐かしくて、安心している自分もいました。
ふたりの身体が、ぴたりと重なった瞬間──言葉なんて要らない、と心から思いました。夫の動きはゆっくりで、でも確かで、ただ静かに、何度も何度も彼を受け入れました。年を取っても、心と体が求め合うということがあるのだと、私はこの夜、初めて知ったのです。
私の名前は、玉木ひろ子。60歳になりました。夫の博も同い年です。つい先日、今年で31歳になる末娘の美和が、「彼と一緒に住む」と言って家を出ていきました。いまどきの子ですから、結婚前に同棲というのも、驚くようなことではないのかもしれません。
でも正直、私は驚きました。いや、驚いたのは私以上に、夫の方だろうと思っていたのです。博は、いわゆる昭和の男です。昔気質で、娘が変な格好をしていれば眉をひそめるような人でしたし、私が若い頃は「亭主関白」そのもののような人でした。
長女の時なら絶対許さなかったと思います。だからてっきり、「何を考えてるんだ」と怒るかと思っていたのですが……そうではありませんでした。娘が出ていく日、夫はむしろ静かに、「気をつけてな。困ったらすぐ戻ってこいよ」と、ただそれだけ。美和も驚いたような顔をしていました。
私は、その時の夫の横顔を、じっと見つめてしまいました。怒ることもせず、反対するでもなく、娘の人生をそっと背中で支えるようなその姿が、どこか頼もしく見えたのです。そして同時に、ああ、これで本当に「家族」というかたちが一区切りついたんだな、と実感しました。 その日の夕方、荷物を全部運び終え、娘が出ていったあとの家は、想像していた以上に静かでした。三人の娘たちが順に巣立ち、ようやく夫婦二人だけの生活に戻ったのです。
なのに私は、その静けさに、少し戸惑っていました。あんなに「夫婦の時間が欲しい」と思っていたのに、いざ手に入れてみると、どう接したらいいのかが、わからなかったのです。
夕食後、テレビの前で並んで座る。夫はビールを飲みながらプロ野球を見ていて、私は台所で洗い物をしながら、心のどこかで考えていました。
娘がいた頃は、何かと話題もありました。けれど今は、家の中にいるのは、夫と私だけ。夫婦として、改めて向き合うことになる。そう考えると、ちょっとだけ、怖くなりました。
でも、博は私の不安を察していたのかもしれません。その夜、いつもより少し早くテレビを消し、私の湯呑みを手に取り、「ほら」と渡してくれたのです。何年ぶりかで、まっすぐ私を見ながら──。
そこから、今夜のようなことに繋がっていくなんて、あの時の私はまだ想像していませんでした。でも、身体は覚えていたんです。夫に触れられる感覚を。そして、なによりも、「女として見られること」の喜びを──。
あの夜を境に、私たちの時間は少しずつ、けれど確実に変わっていきました。目覚めた朝、夫の寝息が隣で静かに続いているのを確認してから、私はそっと布団を抜け出しました。台所に立つ手は自然と丁寧になり、湯気の向こうで鼻歌なんかを口ずさんでいる自分に気づいて、思わず笑ってしまいました。若い頃のように派手な変化ではありません。でも、鏡の前に立つ自分の顔つきが、ほんの少しだけ柔らかくなった気がしました。肌のハリはなくなっても、眉間の皺も薄くはならなくても、それでも「誰かのために整える」という気持ちは、やっぱり女を元気にするものなのだと、私は実感しています。
夫も変わりました。口数は相変わらず少ないけれど、私の作った料理に「うまいな」と言葉を添えてくれる回数が増えました。夕飯のあとの食器を、黙って水に浸してくれていたり、洗濯物を黙って取り込んでくれていたり、そんな細やかな気遣いに、私は毎日小さな「ありがとう」を感じています。
そして──夜。毎晩というわけではありません。でも、ふとした夜に夫が肩に手を置いてきたり、寝室に入ってきて隣に静かに座るだけで、私は「ああ、今日もそうなんだな」と心のどこかで覚悟と期待が交じったような気持ちになります。
60歳という年齢で、まさかこんなふうに夫とまた肌を重ねるようになるなんて、正直言って思ってもみませんでした。年齢のことを考えると、恥ずかしい気持ちもあります。でも、あの人の手に触れられるたび、私は不思議と安心してしまうのです。
若いころのそれとは違います。激しさも、勢いも、たぶん少しだけ鈍くなっているかもしれません。けれど、丁寧で、優しくて、まるでひとつひとつの動作に「大切にしているよ」と書き込まれているような、そんな触れ方をされると、私の身体も自然と応えてしまいます。
ある晩のことでした。浴室から出たばかりの私を捕まえて、求めてきたのです。私は思わず小さく震えてしまいました。タオル越しに肌を撫でられるだけで、体の奥に静かな熱が宿っていく。胸の下からじんわりと広がって、呼吸が少しずつ浅くなるのがわかる。
彼が、私の耳元に口を寄せて、何も言わずに吐息を落としたとき──私は、全身がほどけてしまいそうでした。
こんな私を、まだ女として扱ってくれることが、ただただ嬉しくて、涙が出そうになるのです。
触れ合うたび、私は「女」に戻っていく気がします。母でもなく、主婦でもなく、ただの「私」として。
そして、あの人もまた、「父」でも「亭主」でもなく、「ひとりの男」として、そこにいるように思えます。
日中の会話も、少しずつ増えてきました。娘のこと、昔話、時々ニュースのこと。
「昔、お前さ、あの時俺に黙って旅行の予約してただろ」そんな他愛ないやりとりが、今では愛しくてなりません。
私たちは、今になって、ようやく夫婦に戻れたのかもしれません。子育てに追われ、仕事と家事に振り回されて、ずっと「親」としての時間しか持てなかった日々。そのすべてがひと段落して、今ようやく、私たちはふたりだけの時間を取り戻しつつあるのです。
ある晩、寝室の電気を消してから、夫がぽつりと言いました。
「……またこんな風にできるなんてな」私は暗闇の中で、そっと手を伸ばして彼の指を握りました。
「ありがとう」とは言えなかったけれど、その手に込めた気持ちは、きっと伝わっていたと思います。
私の人生は、もう終盤に差しかかっています。でも、終わりだなんて、もう思いません。
こんなふうに、夫に見つめられて、肌を重ね、心を通わせて──たとえ何年かぶりでも、何十年ぶりでも、
愛し合うことは、きっと、いつだって「今から」始められるのだと思うのです。
そして、こうして私の髪を撫でてくれる手がある限り、私はこれからも、女でいられる。そう信じています。