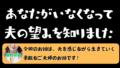私の名前は寿郎、65歳です。先日、妻の初枝が転んで足を骨折し、今は病院に入院しています。いつもそばにいた彼女が突然いなくなった生活に、何とも言えない寂しさを感じています。
初枝が入院してからというもの、家は急に静かになりました。二人で過ごしていた時間が、今は私一人きりの時間に変わってしまったからです。朝起きると、いつもなら朝食を用意してくれていた初枝の姿がない。空っぽの台所を見ると、これが現実なのだと改めて実感します。料理なんてほとんどやったことがない私が、仕方なく冷蔵庫の中を探し、適当に何かを食べる日々です。食事の時間がこんなに味気なくなるとは思いもしませんでした。
私たち夫婦には娘がいますが、もう何年も会っていません。最後に会ったのは、あの日、大きな言い争いをして家を出て行ったときでした。娘の名前は真奈美。まだ若かった頃の話ですが、真奈美が進路のことで相談に来たことがありました。彼女は音楽の専門学校に進学したいと言っていましたが、私は反対でした。安定した仕事に就くためには、もっと現実的な進路を選ぶべきだと強く言ったのです。「食っていける保証もないし、そんなことを夢見て現実を見ないのは馬鹿げている!お前はいつか結婚をするんだろ!?」と声を荒げました。
はっきり言って大人気なかったと思います。もっと子どもに寄り添ってやるべきだと思いました。私がこんな調子で怒鳴り散らしたので真奈美も負けずに反論し、「お父さんは何もわかってない!」と泣きながら怒鳴り返しました。あの時、私はただ「家を出て行け」と言ってしまった。それ以来、娘は本当に家を出てしまい、連絡も取らず、もう何年も会っていません。怒りに任せて発言するなんてやってはならないことだったと思います。
その後、私と初枝は二人で暮らしてきました。決して仲が悪いわけではありませんが、私は昔から威張るタイプで、何かと言えば初枝に指示を出すような態度を取っていました。朝食のメニューに文句をつけたり、掃除のやり方にケチをつけたり。初枝は「はいはい」と言って、文句も言わずに私の言うことを聞いてくれました。だからといって、特に感謝の言葉を口にすることもなく、それが当たり前だと思っていたのです。
初枝が入院してから、私は初めてその「当たり前」がどれだけ大切だったかに気づかされました。反省しているという一言では片付けられないくらい、私は初枝に対して迷惑をかけたと今思っています。私なんて初枝がいなければ何もできないただの男です。朝の食卓での何気ない会話や、テレビを見ながらの取り留めのないおしゃべり。それら全てが、今は無くなってしまいました。一人でテレビを見ても、ただの雑音に感じてしまう。新聞を読んでいても、誰かと話すことがなければ、ただ文字が並んでいるだけです。
家の中が静かすぎて、初枝の声が恋しくなります。誰かに威張り散らす相手がいないと、こんなにも退屈になるのかと、自分でも驚いています。それでも、威張りたいわけではなく、ただ彼女の「はいはい」と言ってくれる穏やかな声が欲しいのだと、ようやく理解しました。ですが、そのことを初枝に伝えるのは、やはり恥ずかしい。だから今も、何も言えずにいます。
この数日、夕食後にぼんやりと居間に座りながら、初枝が戻ってくる日を待ち続けています。電話で話すこともできますが、やはり顔を見て話したい。あの安心感が恋しいのです。でも、どこか気恥ずかしさもあって、どうしても素直にはなれないままです。
初枝が入院してからというもの、私は毎日のように病院へ足を運んでいます。初めはただ「近くに用事があったから」とか「ついでに寄ってやる」といった理由をつけていましたが、それが嘘だと初枝にはお見通しのようで、私が病室に入るといつもにっこりと微笑むのです。「お父さん、今日はどうして病院に来たの?」「ふんっ、お前に家のことで聞きたいことがあったから寄っただけだ。こっちは一人で毎日大変だよ」と言ってその笑顔を見るたびに、心の中のもやもやが少しずつ和らぐのを感じていました。
初枝が病院でリハビリを頑張っている姿を見るたびに、私は複雑な気持ちになります。自分一人ではうまくできないことが増えたのに、それでも文句を言わず、笑顔で励ましの言葉をかけてくれる初枝に、私は何も返せていないような気がして。だからといって、「心配してる」と口に出すのは恥ずかしくてできません。私はいつも「まだまだだな」とか「俺がいないとお前は寂しいんじゃないのか?」と、素直じゃないことばかり言ってしまいます。それでも、初枝は「そうですね」と優しく微笑んでくれるのです。
そして、ついに退院の日がやってきました。病院の入口で待っていると、リハビリを終えて車椅子に乗った初枝が姿を見せました。「おかえり」と声をかけようとして、つい「ああ、来てやったぞ」と不愛想に言ってしまいます。でも、本当は初枝が戻ってくるのを、心の底から待ちわびていました。
初枝は私の言葉にクスリと笑い、「お父さん、一人にしてしまってごめんなさいね。今日からまた私がお世話します」と言いました。その言葉を聞いた瞬間、胸がぎゅっと締め付けられるような感覚がしました。私は何も言わずに、ただ「ふんっ、俺の方がうまくやれるから、お前はまだ休んでろ」とつっけんどんに返しましたが、実際のところは初枝の体を心配していたのです。無理をさせたくない、もう転ばせたくない。それだけが、私の本心でした。
初枝を連れて家に帰る途中、彼女がぽつりと話し始めました。「ねえ、お父さん。そろそろ真奈美と仲直りしたら?」その言葉に、私は思わず眉をひそめました。「なんで今さらそんな話をするんだ」と反論しようとしましたが、初枝は続けて言いました。「今回の入院で、もし真奈美がいてくれたらお父さんの世話をしてくれる…って、何度も思ったんです。私たち二人よりも、あの子がそばにいてくれたら、どんなに安心できるかと」
初枝の言葉には、少し寂しそうな響きがありました。それを聞いて、私はしばらく黙り込んでしまいました。娘の真奈美のことを思い出すと、あの時の言い争いの記憶がよみがえります。私の頑固さが原因で、あの子は家を出ていった。自分でもそれが分かっているのに、どうしても素直に謝れないまま、時が過ぎてしまいました。でも、初枝が入院している間、もし娘がいてくれたら、どれほど頼もしかったか。初枝の寂しさを埋めることができたかもしれない、と考えると、心が痛むのです。
「まあ、考えておいてやるよ」と、私は初枝に向かってそっけなく言いました。本当は、少しずつ考えていたことだったのです。あの時のことを謝りたい、そして真奈美とまた話がしたいと。それでも自分の意地が邪魔をして、なかなかその一歩を踏み出せずにいました。でも、初枝がそうして背中を押してくれるのなら、もう少し勇気を出してみてもいいかもしれない。そう思った瞬間、初枝は「ありがとう」と言って、ほっとしたように笑いました。
その笑顔を見た時、私は初枝にこれ以上迷惑をかけてはいけないと、改めて心に誓いました。娘との仲を修復することが、初枝を安心させる唯一の方法かもしれない。私もそろそろ娘に電話をして、あの時のことを話してみるべきだろう。家に戻ったら、まず真奈美に電話をかけてみようと、初枝の笑顔を見つめながら心に決めました。