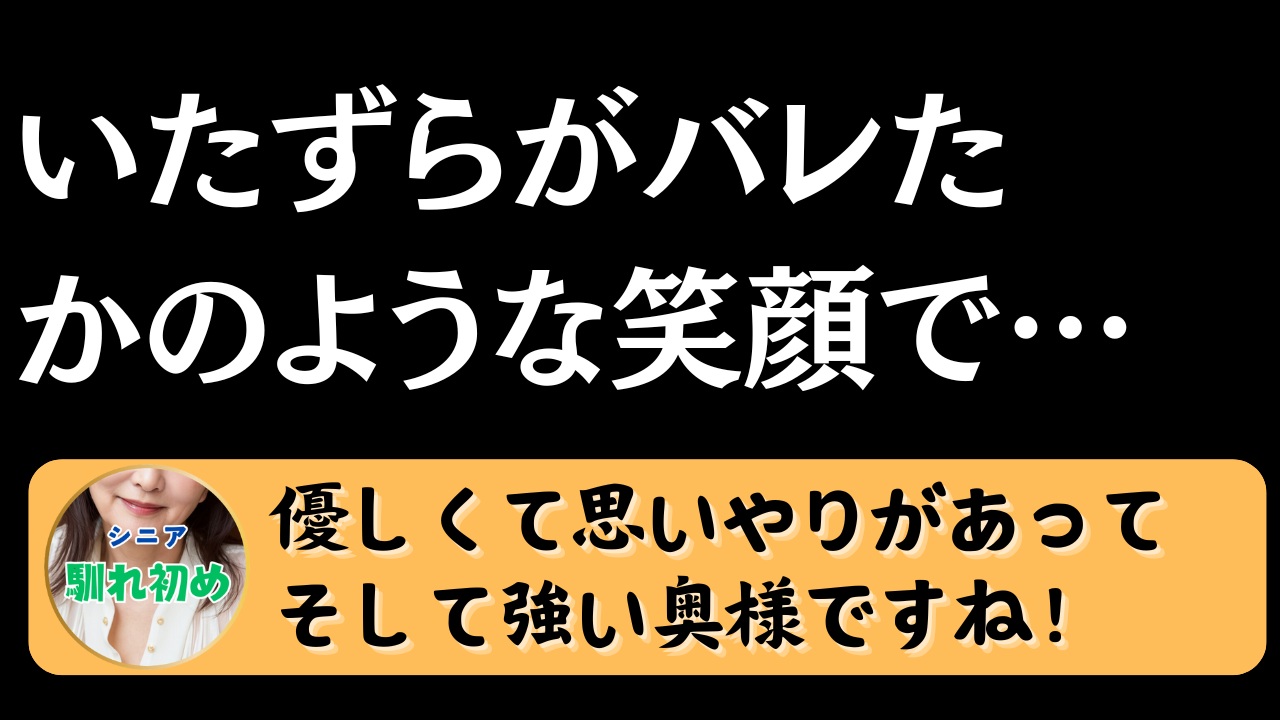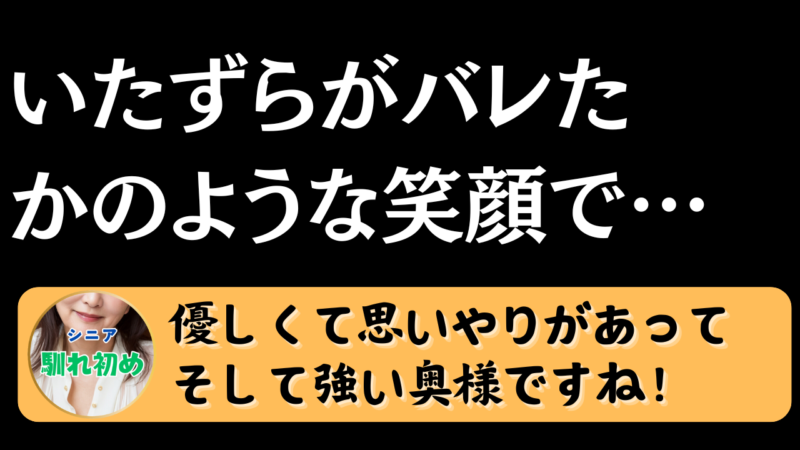
俺の名前は庄司孝之68歳。銀行員として定年まで働き、老後は妻の晴美と悠々自適とまではいかないがある程度好きなことをして生きていこうと決めていた。俺はどちらかと言えば仕事優先な部分があり、家族サービスを満足にできなかった自覚があります。特に晴美には家事や育児をほぼすべて任せていて大変な思いをさせていました。
晴美は「仕事が忙しいんだから仕方ないよ」と、あまり大変さを感じさせないよういつも明るくふるまっていたことを覚えています。だからこそ、定年後は晴美の行きたい場所、欲しい物を出来る限り叶えてあげたいと思っていたんです。
それなのに、俺が定年を迎えて半年もしないうちに晴美は人が変わったようになりました。今までは何も言わなかった家事のことなどを口うるさく言うようになったんです。
「茶碗くらい洗ってくれてもいいんじゃない?」
「定年したんだから洗濯くらいしてほしいんだけど」
確かに今まで俺が何もしなかったことは悪かったと思いますが、だからと言って仕事をしなくなった途端に人が変わったように口うるさくなるなんていかがなものなのかと考えてしまいます。ただ、晴美に言われて家事を少しやっただけですがなかなか大変です。茶碗は適当に洗っても米がこびりついて取れないし、洗濯は衣類ごとに分けて洗わないといけないし、今までしてこなかったからこそ余計に大変さが分かったような気がしました。
「なぁ、俺が定年してから家事について口うるさく言ってくるけどどうしたんだ」
「今まであなたを甘やかしすぎたかなって。もし私がいなくなったらどうするの?」
それを言われると反論の余地もありません。確かに晴美に任せきりで家事をほとんどしたことがなかったからこそ、今の俺がこんなに苦労しているのだから。
「でも、あなたって壊滅的に家事が下手だったのねぇ。ちょっと意外だったわ」
ため息交じり、そして呆れたように言われるとさすがの俺もショックです。最初、家事について口うるさく言われ始めた時、俺は家事なんて楽勝だと考えていました。難しい仕事もそつなくこなしていたし、自分は比較的なんでもできる方だと考えていたからだ。仕事と家事は違うという簡単なことにさえ気づかないのだから、俺は相当晴美に頼り切りだったということだろう。
「ねぇ、思い切ってこれ買っちゃいましょうよ」
晴美が見せてきたのは家電のカタログだった。食洗器に全自動洗濯機、そしてお掃除ロボなどさまざまな便利グッズが載っている。ただ、便利な分なかなか金額が高いのも事実だ。
「いや、わざわざそんなものを買わなくても――」
「まさか今まで通り私がすればいいと思ってる?」
俺の言葉を遮るように話しかけてきた晴美の言葉にぎくりと肩を震わせた。俺が言おうとしていたことはまさに一言一句違わずその通りだったからだ。晴美の冷たい視線がどこか痛くて、俺はスッと視線をそらした。
「あのねぇ、そりゃ私がすれば簡単に終わりますよ?でも、あなたは定年して今は家にずっといる、現役時代の時と同じで考えていたら身体はすぐなまってしまうの」
確かに晴美の言う通りかもしれない。定年してから特に趣味もなく、家でゴロゴロしていたせいか一回り近く太った気がするし、立ったり座ったりが以前ほど簡単にできなくなっている。
「私が楽になりたいという思いもありますけど、あなたの身体のためを思って言ってるのよ」
「……はい」
晴美の言葉に反論することができず、俺はしょんぼりとしながら頷いた。苦労させた晴美のために何かしたいと考えながら、特別なことばかりを考えて身近なことを手伝おうとしなかったなんて俺はどこまで自分勝手で最低なのだろうかと自己嫌悪に陥ってしまう。
「とりあえずひとつずつ家電を揃えていかない?それでできることを増やしていきましょ」
「分かった」
とりあえず、まずは全自動洗濯機を買うことにした。食洗器を買うまでは晴美に茶碗を洗ってもらい、洗濯を俺の係にした。そして食洗器やお掃除ロボットを買い、俺も家事の負担を増やしていった。そして、俺も自分でできることが増えた時、とあるものを見つけてしまった。それを見て、俺は愕然としてしまい、思わず持っていた茶碗を落としてしまうほどだった。
そして、その日の夜。俺は晴美が隠していたものを目の前に突きつけた。
「あら……」
「リビングの棚、しかもかなり分かりにくいところに入っていた」
俺が見つけたもの、それは病院の診断書だった。診断書を見ると晴美は病気だった。しかも、かなり厄介なもので恐らくそう遠くないうちに晴美はこの世を去ってしまうことになる。その病気について何度も調べたけど、晴美ほど進行していれば治るのはほぼ無理だという無情な現実を突きつけられるばかりだった。
「バレちゃった」
晴美はまるでイタズラがバレたかのような言い方をする。それが余計に腹が立って「どうして教えてくれなかったんだ!」と怒鳴ってしまった。違う。怒鳴りたいわけじゃない。だけど焦っているのが俺ばかりで、ある程度受け入れている晴美に腹が立ってしまったのだ。
「まさか、俺に家事をしろと言っていたのは自分がいなくなると分かっていたからか?」
「……そうね。最初に診断を受けたのがあなたが定年してしばらく経った頃だった」
時期を聞くと、俺が定年して半年くらいの頃だ。つまり晴美が家事について口うるさくなり始めた時期と一致する。俺は問い詰めた。どうして治療しようとしなかったのか、どうして俺に病気のことを話してくれなかったのか、と。
「だって、あなたのことだから泣いちゃうでしょ。あなたはそっけないように見えるけどやさしい人だから、きっと子供みたいに泣いちゃうじゃない。離れたくないって」
晴美の言葉は正しいだろう。今現在も「俺を置いて逝かないでくれ」とすがりたいくらいだ。晴美は病気になった後も俺のことばかり考えていたんだろう。このまま自分がいなくなれば、何もできない男が取り残されるだけになってしまうと。だから口うるさくしてでも、俺に家事ができるようにしたかったのだと答えた。
「馬鹿か、お前は。病気になった時くらい自分のことを……!」
「そうしようと思ったけど、私のやりたいことがあなたのために何かしたいだったんだもの。それにこの病気は分かった時から治療しても完治がほぼできないだろうって言われていたの。だから、もっと早くに気づいていればなんて思わないでね」
晴美の言葉に俺はとうとう泣いてしまった。子供のように泣きじゃくる俺を抱きしめながら「仕方ない人ねぇ」と笑いながら母親が子供をあやすようにぽんぽんと背中を叩いてくる。
「私は、あなたと結婚してすごく幸せだったんだから後悔しないでね。あなたが後悔すると、私の気持ちまで否定するってこと、ちゃんと覚えていて欲しい」
それから2年後。晴美は闘病の末にこの世を去った。医者が言うには、本来ならもっと早く亡くなっていてもおかしくないほどの症状だったのだとか。だけど苦しさやつらさをおくびにも出さず、晴美は笑顔のままこの世を去っていった。その後の俺と言えば、まだまだ家事は得意ではないし慣れない部分もあるけどなんとかできている。
「お父さん、お母さんが亡くなったら家事なんてしなくなるかと思っていた」
晴美が亡くなってからしばらく経った頃、子供からそんなことを言われた。確かに最初は俺も続かないだろうと思っていた。でも、家事をすれば晴美と過ごした時間を思い出せるのだ。苦労した部分、失敗した部分、そんな時に晴美は「まったく仕方ないわねえ」と笑いながら手伝ってくれたことを思いだせる。ある意味、家事は晴美からの形見のようなものになっていた。だから、俺は今日も家事をする。いつか晴美のところに行った時「ちゃんと最後まで頑張ったんだぞ」という報告をするために。
いかがでしたか。孝之さんのお話でした。今!が続くことはありません。皆様も悔いのないようにお過ごしくださいね。ではまた。