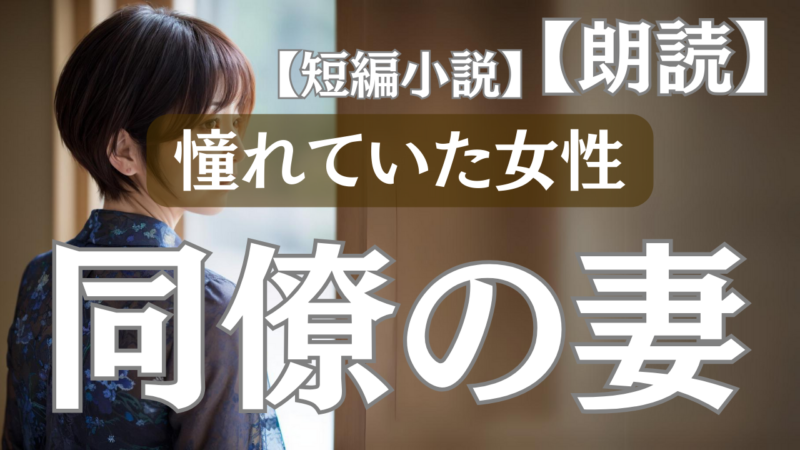
信二は、今までにない状況に直面していた。同僚のあきらの妻、さくらを、深夜に介抱しているという事態だ。お椀に移し変えたうどんを冷ましてから、細かく刻んで、彼女の口元へと運んでいた。単なる介抱のはずが、さくらの艶めいた唇に目を奪われ、心臓が雷のように激しく鼓動するのを感じていた。
今日は同僚のあきらのストレス発散に付き合っていた。夜は更けていき、街は静寂に包まれていた。そんな中、またしても酔いつぶれた同僚のあきらを、今日は信二が家まで送る羽目になっていた。仕事での失敗から、上司に叱責されたあきらは、そのストレスを飲酒で酔いつぶれてしまったのだ。
いつもは、あきらの妻、さくらが迎えに来ていた。さくらは、元は同じ会社の受付で働いており、あきらにはもったいないほど可愛らしく、若々しく雰囲気のある女性だ。もうすぐ40になるとは思えないほどだ。実は、信二もひそかに憧れていた。結婚すると聞いた時はあきらを妬んだほどだ。
しかし今夜は、さくらが体調不良とのことで、信二が送ることになった。彼女の家に着いたとき、いつもの出迎えはなかった。ドアが開いていることに気づき、「さくらさーん」と声をかけるも、返答はない。不安を感じながら家に上がると、彼女はソファで横になっていた。
「すみません、動けなくて…」と彼女は弱々しく言った。ぎっくり腰で3日前から動けないとのこと。信二は、この状況を早く聞いていれば、もっと早く帰らせたのにと謝罪した。「いえいえ、いつものことなので、良いんです。私のことなんていつもほったらかしなので」
あきらをベッドまで運び、「さくらさん、何か手伝いましょうか?」と尋ねると、食事もしていないとのこと。冷凍うどんがあるとのことなので、それを温め、さくらさんに食事を持っていった。しかし、さくらは起き上がることすらできなかったため、結局信二が食べさせることになった。
お椀に移し、ある程度冷ましてからうどんを刻んでスプーンで口に運ぶ。そのとき、さくらの艶めいた唇に目を奪われ、心臓が雷のように激しく鼓動するのを感じた。
表面上は落ち着いて会話を交わしながらも、心の奥底では心臓が胸を打ち破りそうなほどに緊張していた。「他になにか手伝いましょうか?」すると、さくらは黙っている。何か言いたそうだが恥ずかしそうに、そして切羽詰まったような目をしていた。信二は体が硬直するほど緊張したが、発せられた言葉はお手洗いに連れて行って欲しいとのことだった。拍子抜けしたがそれでも、以前ひそかに憧れていた女性を抱き上げるなんて、頭の芯までのぼせてしまいそうだったが、意を決してトイレに抱え上げて連れて行った。信二がさくらをそっと抱き上げた瞬間、彼女の体温が彼の腕を通じて伝わってきた。さくらの体重は彼の腕の中で驚くほど軽く、彼女の存在が一層実感として彼の心に刻まれた。部屋の柔らかい照明が彼女の顔を照らし、柔らかい表情が信二の心を和ませた。そして、さくらの髪から漂う優しい香りが、信二の鼻をくすぐる。その瞬間、全ての世界が彼女に集約されたような錯覚に陥りながらも、必死に理性の糸を手繰り寄せていた。用を足した後、さくらを再び抱き上げてベッドまで運ぶ。「さくらさん、一人で無理しちゃダメだよ。俺にできることなら何でも言ってね」。そして、あきらにもしっかり言っておくと約束した。さくらは、その優しさに感謝し、目に涙が潤んでいた。
信二は、部屋を片付け、別の部屋でのんきに寝ているあきらを「ちゃんとしろよ」と小突いてから家を出た。外に出ると、夜風が冷たい。しかし、信二の心は、さくらへのひそかな憧れと、さらに新たな感情が芽生えていた。家に帰る道すがら、信二はふとした瞬間にもさくらの感触を思い出しては心を乱されていた。ただの憧れが、今や彼女を守りたい、彼女のそばにいたいという切実な願望に変化していたことに、彼自身が驚きつつあった。この夜の出来事は、自分の人生において何が本当に大切なのか、これから何を最優先にすべきなのかを新たに考えていた。


