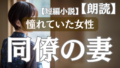冷たい夜風が、俺の心をざわつかせていた。その日、俺と妹の間には、いつも以上の緊張が漂っていた。「か、勝手に見ないでよ!」彼女の声には、慌てふためきと戸惑いが混ざり合ったものだった。俺が彼女のスマホを勝手に見たことに、彼女は顔を真っ赤にして怒っていた。「忘れてたから電話かけただけだろ」と言い合いになり、彼女は外に飛び出していった。それから間もなく、突然、ブレーキの音と衝突の音が響き渡った。何が起こったのかと外に駆け出すと、信じられない光景が目の前に広がっていた。妹が、頭から血を流し静かに地面に横たわっていたのだ。
俺の名前は達也。血のつながらない妹、知美との関係は、両親の再婚によって突如として始まった。彼女に初めて会ったとき、その透明感に心を奪われた。始めはお互い緊張しながらも、良い関係を築けていた。しかし、時間が経つにつれて、会話も少なくなり、些細なことで言い争うことも増えた。そのせいで居心地が悪くなり、俺は高校を卒業すると同時に家を出た。
だが、知美も高校卒業後に上京し、度々俺の家を訪れるようになった。理由は母が作ったという冷凍のおかずを分けてくれるためだ。彼女が家の中を整えたり、心遣いを見せるたびに、俺はそれを義務感からの行動だと思い込んでいた。高校時代のように言い合いになることは少なくなったが、やはり時々、小さな衝突は避けられなかった。
20年の時が経ち、俺も40代が近づいていた。俺はモテないから結婚できないのは分かるが、仲はあまり良くなくても妹は誰の目から見ても美人だ。高校時代のままの透明感に、さらに大人の色気も加わってさらに魅力的になっていた。
その日も、いつものように妹が冷凍のおかずを持ってきてくれた。だが、彼女は上着を忘れて帰ってしまっていた。取りに戻るように電話をかけると、そこにある上着の中から着信音がした。そしてそのスマホを取り出し、表示されている名前を見て驚いた。「お兄ちゃん」の横に「大好きな人」という絵文字が添えられていた。さらに、俺の写真が表示されていた。知美のスマホを持っているその時、焦った様子で知美が戻ってきた。知美は「か、勝手に見ないでよ!」と叫び、「忘れてたから電話かけただけだろ」と言い合いになり、そして彼女は家を出だしてしまった。
間もなくして、恐ろしいブレーキの音と衝突の音がした。外に飛び出してみると、信じられない光景が目の前に広がっていた。血を流し倒れている知美を見て、俺の体は震え、絶望で心が引き裂かれたようだった。
病院で、両親と共に彼女が目を覚ますのを待っている間、俺は知美がどれほど自分のことを大切に思ってくれていたのかを知った。母が送ってきたと思っていた冷凍おかずは、実は知美が毎回手作りしてくれていたものだった。彼女の深い愛情を知り、俺は自分の鈍感さを恥じながら、彼女の回復を切に願った。
手術が成功し、彼女がようやく目を覚ました時、俺は涙を隠せなかった。「お兄ちゃん」と弱々しい声で呼ぶ彼女に、「知美、本当にごめんな。」と謝ると、彼女も涙を流しながら微笑んだ。その瞬間、俺たちの間に流れていたすべての誤解と距離が、深い愛情に変わったように感じられた。
俺たちの関係は、これまでのものとは全く違うものへと変化していく。それは、互いの真の気持ちを知ったことで、新たな一歩を踏み出したからだ。言葉にはできない深い絆が、俺たちを強く結びつけていた。