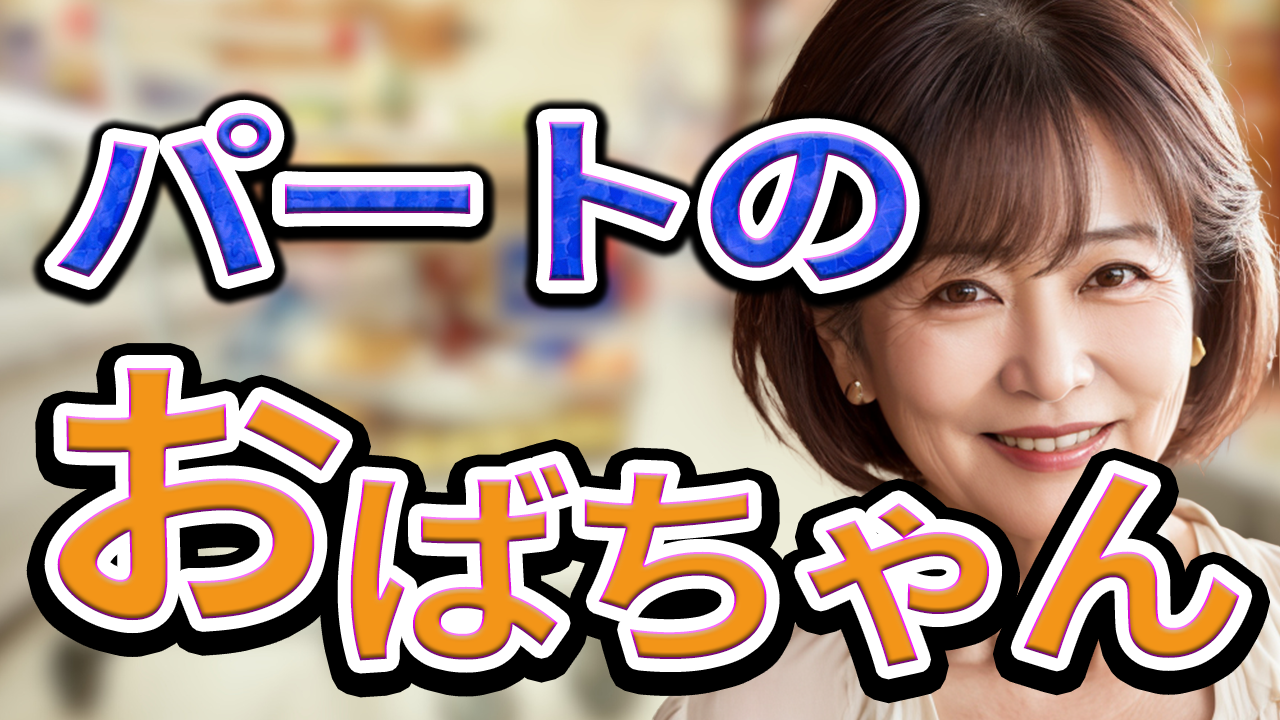私の名前は新見利一、62歳です。
定年退職後に働き出したスーパーで、ふと気が付くと、私の手のひらに温かい感触が触れていました。ふくらみのある柔らかい指先が、戸惑ったように動いて、すぐに離れていきました。
「あっ、ごめんなさい!」
美穂さんの声が、驚いたように少し弾みました。私は反射的に彼女の方を向くと、彼女が軽く手を引っ込めながら、申し訳なさそうな表情で微笑むのが目に入りました。彼女の視線は私の顔を見たり手元を見たりと少しオロオロとして、彼女自身が気まずそうに感じているのがわかりました。
「いえいえ、気にしないでください。本当に大丈夫ですよ」
私は慌ててそう言いましたが、内心では、心臓がドキドキと不規則な鼓動を打っているのを感じていました。まるで学生時代、初めて異性と手が触れたときのような、場違いな胸の高鳴りでした。
「すいません、よそ見しながら商品を取ろうとしてたら、つい…。本当にすみません」
彼女はそう言いながら控えめに微笑みました。その笑顔は、ほのかな明るさをまとっていて、声の柔らかさも相まって、どこかホッとさせる力を持っていました。
それでも、たった一瞬の触れ合いがこんなに鮮明に残るなんて、驚きました。60歳を過ぎた今、もうこういう感覚は遠いものだと思っていたのです。でも、そのとき感じたぬくもりは、私の心に想像以上に深く刻み込まれていました。
私は定年を迎え、長年続けたサラリーマン生活を終えてから数年が経ちました。最初のうちは、時間に追われることがない生活が新鮮で、朝の散歩や趣味の読書を楽しんでいました。でも、そんな日々も長くは続きませんでした。時間がたっぷりあるというのは、裏を返せば何もしていない時間がたっぷりあるということです。さらに、年金が入ってくるまでどんどんと貯金が減っていきます。その為節約しないと、と思い遊びに行くことすらできませんでした。
家にいる時間が増えると、妻がイライラしてるのもやはり感じます。自然と会話も少なくなり、気がつけば、どこかよそよそしい空気が家に漂うようになっていました。些細なことで口論になることも増え、どちらが悪いというわけでもないのに、なんとなくお互いに居心地の悪さを感じていたのです。
そんな日々に耐えかねた私は、地元の小さなスーパーでパートを始めることにしました。働くのは久しぶりのことだったので、最初は少し気恥ずかしさもありましたが、家にいるよりはいいだろうという気持ちで決心しました。妻も「それくらいがちょうどいいんじゃない」と軽く背中を押してくれましたが、その言葉にもどこか棘のような冷たさを感じたのを覚えています。
スーパーでは、棚に商品を並べたり、バックヤードで在庫を整理したりする裏方の作業を任されました。サラリーマン時代は営業一筋で、スーツを着て人前に立つのが日常だった私にとって、体を動かす作業系の仕事はまるで別世界。正直、かなり苦戦しました。
最初のうちは商品の並べ方も手際が悪く、若いスタッフに注意されることもよくありました。「ここ、もう少しきれいに揃えてください。」なんて言われるたびに、胸の奥にチクリとした痛みが走りました。長年、部下に指示を出す側だった自分が、今ではその逆の立場。その現実を突きつけられるたびに、悔しさや情けなさ、苛立ちでいっぱいになりました。
そんな中、清掃パートの美穂さんの存在が、私の目に自然と映るようになりました。彼女は私と同じくらいの年齢で、控えめな雰囲気を纏っていながら、いつも明るく職場を照らしているような人でした。良い意味で掃除のおばちゃんて感じでした。いつも丁寧な仕事をしており、つい目が止まってしまうのです。
でも、当初の私は彼女と深く関わることはありませんでした。「掃除係」という肩書きを勝手に下に見ていたのかもしれません。それなのに、ある日の休憩時間に彼女と話す機会があり、その印象は大きく覆されました。
「営業マンだったんですか?じゃあ何でも出来ますね。」
そう言われた時、私はつい過去の自慢話から今の愚痴まで、一気に口を滑らせてしまいました。「だから今の仕事が情けなくて…」と半ば情けないというような調子で話してしまったのですが、美穂さんはその言葉に少し驚いた顔をした後、静かに微笑みながらこう言いました。
「仕事に表も裏も、上も下もないんですよ。その時、その場でできることを一生懸命にやれば、それでいいんじゃないでしょうか。」
その言葉が心にしみました。軽く注意されたような気がしたけれど、不思議と嫌な感じはしませんでした。それどころか、彼女の言葉に包まれると、何かにがんじがらめになっていた自分の心が少し軽くなったような気がしました。
それ以来、私は彼女と話す時間を楽しみにするようになりました。休憩中に交わす何気ない会話が、私の心をじんわりと温めてくれるような気がしたのです。
ある日のこと、若いスタッフに注意されたミスを引きずりながら休憩室に戻ると、美穂さんがそっとクッキーの袋を私に差し出してくれました。
「落ち込んでるときは、甘いものですよ。」
その一言が、私には何よりもありがたかったのです。彼女の優しさは、声や仕草に染み込んでいて、私はその温かさに救われる思いでした。
彼女と話すうちに、自分の中に少しずつ変化が生まれていきました。家に帰れば妻との会話も増え、以前のような険悪な空気は少しずつ薄れていきました。心が軽くなるとは、こういうことを言うのでしょう。
「新見さん、また明日も頑張りましょうね。」そう言って美穂さんが微笑むと、私はなぜだかそれだけで心が軽くなるのを感じました。家に帰る道すがら、ふと自分がこうして前を向いて歩けるようになったのは、彼女との何気ない会話のおかげだと思いました。
そのことで家に帰ってからも妻とギスギスすることも無くなり、最近では妻と二人で近所の商店街を散歩することも増えました。以前ならただ黙って歩くだけだったけれど、一緒に歩く妻の表情は、なんだか昔を思い出させるものに変わっていました。