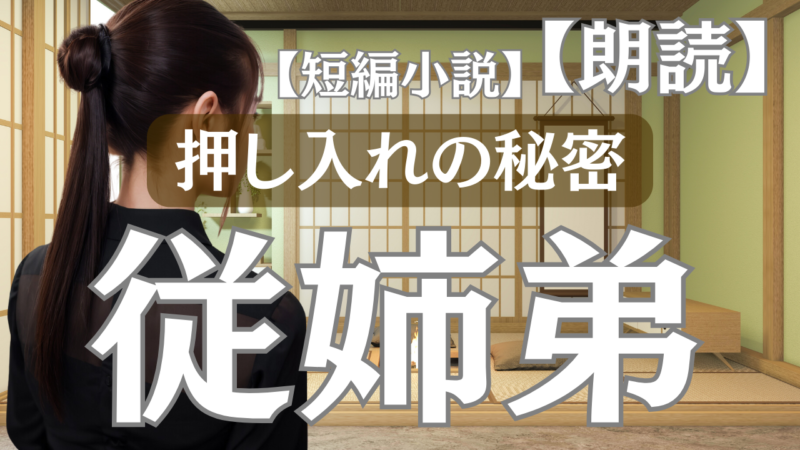
30年前のあの日、俺はいとこの礼子とキスをした。
祖父の葬儀の静かな喧騒の中、ひときわ輝く礼子の姿に目が留まった。30年ぶりに再会した彼女は、悲しみの中にも変わらぬ明るさを湛えており、時を経ても変わらぬ彼女の存在感に、心が熱くなった。30年の歳月を隔てても、あの瞬間の記憶は俺の心に鮮烈に残っていた。彼女はもうすぐ45歳になるというのに、時間を止めてしまったかのように変わらず美しかった。
あの日、俺たちは年下のいとこたちと一緒にかくれんぼをしていた。俺はいつもの隠れ場所、押し入れへと向かった。扉を開けると、そこにはすでに礼子がいた。「ふふ、やっぱりここへ来たのね。」彼女の声に、俺の心が跳ねた。別の隠れ場所を探そうとしたが、礼子は俺を押し入れに引き込んだ。
毎年一度会うだけの関係だったが、俺たちはいつも自然と打ち解け、姉弟のような、友達のような不思議な関係だった。しかし、その年の礼子は何かが違っていた。もはや少女ではなく、大人の女性の雰囲気が漂っていた。狭く密閉された押し入れの中で、礼子の温もりが隣からじわりと伝わってきた。そのぬくもりは、冷え切った季節を忘れさせるかのように、私の心の隅々まで温かさを運び、ほんのりとした甘い緊張感が空気を満たしていった。
「ゆうき、彼女はできたの?」礼子の大人びた問いかけに、俺は恥ずかしさでどう返答していいか戸惑った。かくれんぼのハラハラドキドキとは異なり、心臓がバクバクとなり礼子に聞こえてしまうのではないかというほど鼓動が早まっていた。
「キスしたことある?」。彼女のふいの提案に心臓が跳ね上がる。礼子がゆっくりと顔を近づけてくる。その瞬間、俺たちを取り巻く空気すらも緊張で張り詰め、時が静止したかのような感覚に包まれた。そして、そのまま二人はキスをした。まるで時間が止まったかのような、この世界に二人だけの感覚に包まれた。しかしその瞬間、子供たちがふすまを開けて「みーつけた」と叫んだ。
キスの後、罪悪感と興奮、恥ずかしさが入り混じり、複雑な感情に包まれていた。その後、お互いが大学生や社会人になり、帰省のタイミングが合わなかったりで、会うことがないまま静かに時間が流れていった。しかし、今、祖父の葬儀で久しぶりに再会し、あの時の感情がふたたび蘇ってきていた。
「久しぶりね。元気だった?」久々の再会だったため、お互いぎこちなかったが、お酒の力も入り徐々に会話が弾んだ。その時、礼子がふいに「ねえ、あの時のこと、覚えてる?」と尋ねてきた。「ああ、忘れることなんてないよ」「ふふ、私もだよ。」と答え、お互いに顔を見合わせ微笑み合った。その時、お互いの子供たちが「え?なになに?何の話?教えて!」と興味津々に聞いてきたが、「内緒だよ」と言うと、「えー、なんか怪しい」と子供達は言っていたが、すぐに他のことに気を取られ離れていった。そして、俺たちは誰にも邪魔されることなく、過ぎ去った時を静かに振り返りながら、深い絆と温かな感情を共有し合う、そんな静謐な晩酌を楽しんだのだった。


