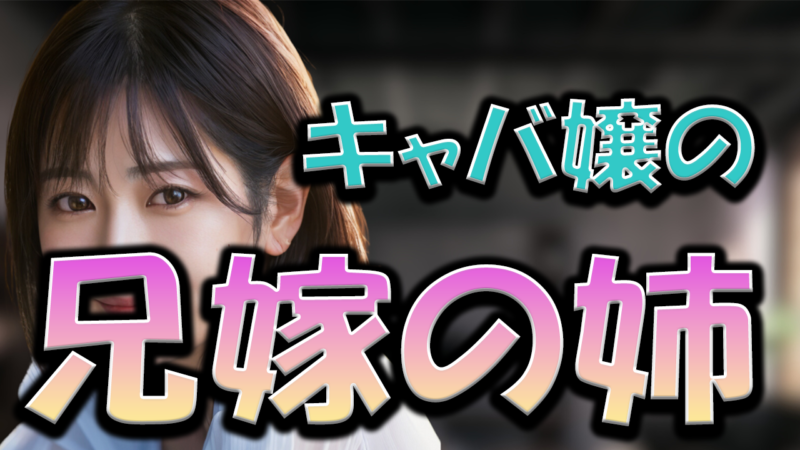
「お兄ちゃんが結婚することになったよ」
母からの電話を受けたとき、俺はちょうど昼休みの食堂で定食をかきこんでいた。
「え、兄貴が?」思わず聞き返す。
「そうよ。正樹がね、ついに結婚することになったの。相手はね、由美さんっていうの。とても素敵な人よ」母の声は嬉しそうだった。
俺の兄、浅井正樹は、真面目で堅実な男だ。
教師という職業柄もあるのか、昔から地道に努力し、慎重なタイプだった。
そんな兄がついに結婚するというのだから、俺も驚いた。
「良かったじゃん。相手はどこで見つけたん?」
「紹介だったみたいよ。ずっと仕事ばかりだったし、なかなか良い出会いがなかったからね」
兄貴の不器用さを考えれば、確かに紹介がなければ進展しなかったかもしれない。
「それでね、来週両家の顔合わせがあるの。直樹も来れる?」
「うん、わかったよ」こうして、俺は兄の結婚相手とその家族に会うことになった。
それから数日後、仕事帰りの電車の中で、ふと「兄貴が結婚かぁ……」と考えていた。兄貴が結婚する。つまり、義理の家族が増えるということだ。
ぼんやりとそんなことを思いながら、過去の記憶がよみがえった。——ミナのこと。二年前、俺はあるキャバクラで一人の女性に夢中になった。
最初はただの仕事だった。取引先の担当者に「接待に付き合ってくれ」と言われ、しぶしぶ同行したのがきっかけだった。
正直、キャバクラなんてあまり興味はなかった。けれど、その店で俺を担当したのが「ミナ」だった。
笑顔が魅力的で、会話が上手で、何より一緒にいると心地よかった。
「初めてのご指名、ありがとうございます♡」ミナは、初対面にもかかわらず、親しみやすい笑顔を向けてくれた。
それが仕事なのはわかっているが、俺はミナのことが気になって仕方なかった。
それから、取引先の付き合い以外でも俺は店に通うようになった。
「直樹さん、また来てくれたんですね。嬉しいなぁ♡」
そんな言葉をかけられるたびに、俺の心は彼女に惹かれていった。何度か同伴もした。彼女と過ごす時間が楽しくて、気づけば会うことが日常の一部になっていた。
「ミナは、なんでキャバクラで働いてるの?」るとき、ふと聞いてみたことがある。「んーちょっとお金がいるんだ。いつか話せる日…かな?」そう言って、ミナは少し寂しそうに笑った。
でも、それを深く追及することはなかった。俺にとって、彼女と過ごす時間が何より大事だったから。
——だけど、ある日、ミナはいなくなった。
「ミナちゃんは、退職しました」店のスタッフにそう告げられたとき、俺の頭は真っ白になった。
LINEを送っても既読がつかず、電話も繋がらない。
まるで、最初から存在しなかったかのように、彼女は消えた。
何度も店の前を通った。何度も彼女の笑顔を思い出した。それでも、俺は結局、ミナに会うことはできなかった。
——そして今。兄貴の結婚で、新たな出会いが待っているはずだった。まさか、その席で、彼女と再会することになるとは思いもしなかった——。
両家顔合わせ当日、俺は少し遅れて会場に到着した。扉を開けると、すでに全員が席についていた。
「遅いぞ、直樹」兄貴が口の動きだけでそう伝えてくる。
「悪い、仕事が長引いて」軽く謝りながら、空いていた席に腰を下ろした。
向かいに座るのは、兄の婚約者の由美さん。
一目見て、「兄貴にはもったいないくらい、美人な人だな」と思った。
穏やかで優しそうな雰囲気で、きっと兄の支えになってくれるだろう。
「そして、由美さんのお姉さんである奈美さんです」由美の隣に座る女性を紹介され、俺は何気なく視線を向けた。
その瞬間、俺の思考は完全に停止した。
——ミナだ。いや、今の彼女の名前は奈美。
「……」奈美もまた、俺をじっと見つめていた。
まるで、「気づいた?」と言いたげな、強い視線で。俺は、目の前の光景が信じられなかった。二年前、何の前触れもなく俺の前から姿を消したミナが。今、兄の婚約者の姉として、ここに座っている。何も考えられない。
まさか、こんな形で再会するなんて——。顔合わせの食事会は、俺にとって味のしない時間だった。話の内容はほとんど頭に入ってこない。そして、トイレに立ったときだった。廊下で俺を待ち構えていた奈美が、静かに口を開いた。
「……明日、連絡してきて」そう囁きながら、彼女はメモを手渡す。
そこには、彼女の電話番号が書かれていた。俺は迷いながらも、それをポケットにしまった。
——逃げることはできない。翌日、俺は覚悟を決めて、奈美に電話をかけた。
「直樹だけど。久しぶり」電話口の奈美の声は、あの頃のままだった。
「話がしたいの。会えないかな?」俺は迷うことなく「いいよ」と答えた。
そして、待ち合わせたカフェで向かい合った俺たちは、ついに本音を語り合うことになる。
「まさかあんなところで会うなんてね」
「あ、あぁ。びっくりしたよ。でも、どうして突然辞めたの?」
「ごめんね…..」奈美は、ゆっくりと口を開いた。
「お金が必要だったのはお父さんの医療費と生活費のためだったの」俺は何も言えなかった。
「……稼ぐためなら、何でもしたの。」奈美の言葉に、俺は一瞬、息を飲んだ。
彼女の表情は、どこか遠い目をしていた。
「……何でも?」そう問いかけながらも、俺は無意識に拳を握りしめていた。
「うん。言えないけどね…」奈美は苦笑しながら、お茶のカップを軽く揺らした。
「ただお金の為だけに夜の仕事を始めたの。でもあれ以上あなたと付き合っていると…」
「汚れてしまった自分が情けなくて…だから、店を辞めたの」それだけ、とでも言うように淡々と語る彼女を見て、俺は何も言えなかった。
「みんなには黙っててくれる?私に負担をかけたと思わせたくないから」
彼女の声は、驚くほど冷静だった。
「ああ、誰にも言わない」奈美は少し驚いたように目を見開いたが、すぐに安堵したように微笑んだ。
「ありがとう」俺はこのとき、彼女の笑顔にどこか救われたような気がした。
それから、俺たちは何度か会うようになった。カフェで話したり、食事をしたり。不思議なことに、昔のように「お客とキャバ嬢」という関係だった頃よりも、今のほうがずっと自然だった。
そして、ある日——。奈美から、突然の電話がかかってきた。
「うちの母がね、いかなごのくぎ煮をたくさん作ったの。持って行ってもいい?」
「え?」
「直樹の家、どこだっけ?」
「え、ちょっと待って……」俺は慌てて部屋を見回した。
——散らかってる。
テーブルの上にはコンビニの空き容器。ソファには脱ぎ散らかしたシャツ。
床には読みかけの雑誌と、片付け損ねた段ボール。
「えっと、大変だろ今度でいいよ?」「別に? ついでに渡すだけだし」
「えー、せっかくだから、お邪魔していい?」
「ちょ、ちょっと待て!」
「もう、今から向かってるから♡」電話が切れた。俺は、血相を変えて片付けを始めた—が、当然、間に合うわけがなかった。
「お邪魔しまーす」奈美が部屋に入るなり、部屋を見回してクスッと笑った。
「ふふ、片付け苦手なんだね」
「……うるさい」俺はソファの上の服を慌ててどかしながら、彼女をテーブルに案内した。
「はい、これ。母が作ったやつ」奈美が手渡してくれた袋の中には、小分けされたくぎ煮が入っていた。
「ありがとな」
「せっかくだし、ご飯作るから一緒に食べようよ」
「え?」
「え、だめ?」
「いや、いいけど……」奈美は手際よくキッチンを片付け、二人分の食事をちゃちゃっと作り上げた。
「おいしいな、これ」「でしょ? 母の得意料理なんだよね」
「お味噌汁も美味しいよ」奈美は満足そうに微笑んだ。
しばらく他愛もない話をしていたが、気づけばビールの缶が3本ほど空いていた。
「ねえ、直樹」ふと、奈美が俺を見つめる。
「……何?」
「直樹ってさ、私のこと、どう思ってるの?」俺は、不意を突かれて言葉を失った。
「……どう、って?」
「私ね、ずっと気になってたの。昔の私のことを知っても、どうして普通に接してくれるんだろうって」
「そんなの、決まってるだろ」俺は、缶をテーブルに置き、彼女をまっすぐ見つめた。
「俺は、あの時から奈美が好きだから」奈美の瞳が、大きく揺れた。
「ミナの頃から、いや……奈美として再会してから、余計にそう思うようになった」俺は、手を伸ばし、そっと奈美の手を握った。
「俺は、過去なんて気にしない。奈美がどんな仕事をしてたとか、そんなの関係ない」奈美はしばらく黙っていたが、やがてぽつりと呟いた。
「……こんな私でいいの?」
「奈美じゃなきゃ、意味がない」
奈美の目から、涙がこぼれた。
そして——
そっと唇が重なった。
俺にとっても、奈美にとっても、これは初めての、本当のファーストキスだった。
「……ありがとう」奈美は俺の胸に顔を埋め、小さくそう囁いた。
俺たちの未来は、ここから始まっていた。


