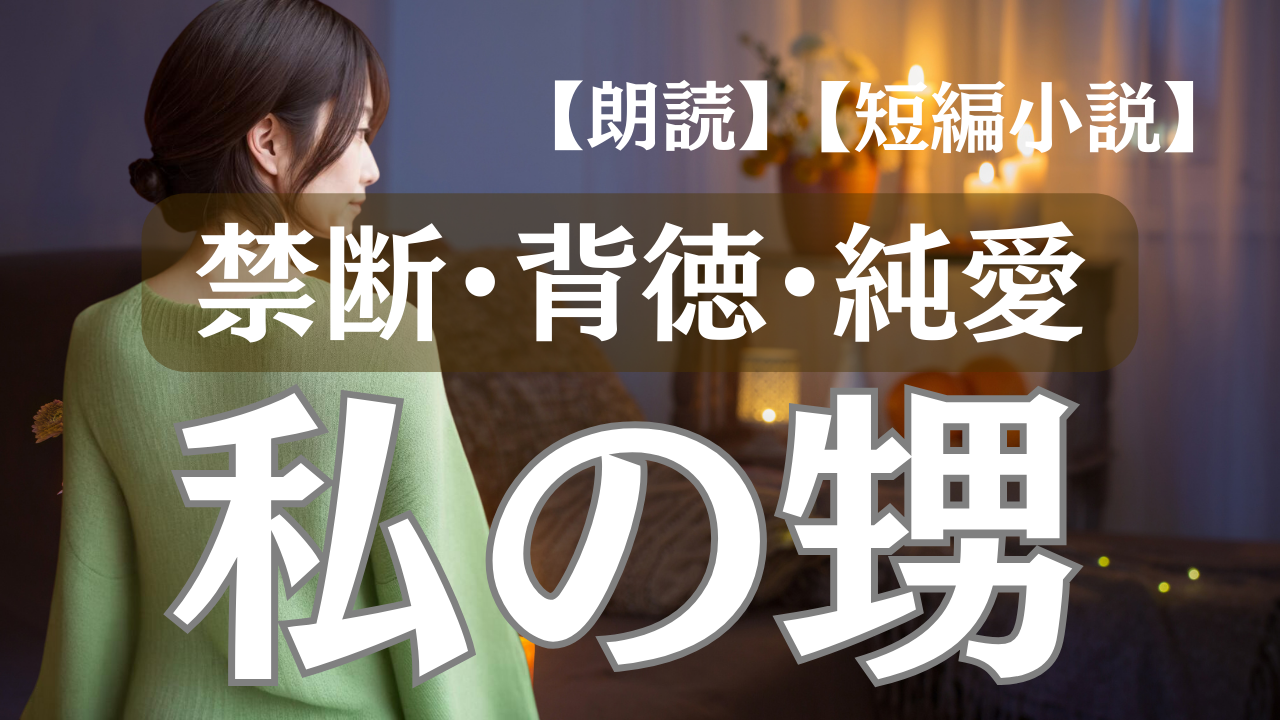悦子はその夕暮れも、達也のために夕食を準備していた。
彼女の料理は、手間ひまかけた愛情の表れ。
今夜は達也の好きな煮魚と季節の野菜を使った一品を中心に、彼女の心を込めたメニューがテーブルを飾った。
悦子はこの時間を特別に思っており、彼女にとって達也はただの甥ではなかった。
達也との夕食の時間は、悦子にとって最も心が温まる瞬間であった。
彼女は、彼の笑顔や話す声の音色までをも心の支えとしていた。
達也は年の離れた兄の息子であり、年は4歳しか離れていないが甥にあたる。
一介の会社員で、誰が見ても穏やかで優しい性格の持ち主。
しかし悦子の中では、達也は特別な存在であった。
達也自身は、悦子を叔母とはいえ姉のように慕っていた。
達也が到着し、悦子は彼を温かく迎えた。
彼はいつものように、無邪気な笑顔で「こんばんは」と挨拶し、悦子の手料理に目を輝かせた。
「こんなに美味しいごはんを毎日食べられるなら、もうここに住んじゃおうかな」
と彼が言った時、悦子の心は複雑な感情に包まれた。
達也がそう言うのは、彼の性格上の気遣いからで、悦子に対する特別な感情からではなかったことを、悦子自身よく知っていた。
彼は悦子を家族のように接してくれているだけで、悦子が抱く感情には気づいてさえいない。
食事の間、二人の会話は軽やかに流れた。
達也は仕事のこと、最近の趣味のことなどを話し、悦子はそれを優しく聞き入れた。
悦子にとって、達也の幸せが何よりの願いだった。
彼が独身でいて私がそばにいれること、それが悦子の密かな希望である一方で、彼の将来を心から願う自分もいた。
達也に対する感情は、悦子自身にとっても複雑で、時に苦しいものだった。
夕食が終わり、二人はソファでコーヒーを楽しんだ。
悦子は達也が子どもの頃から今に至るまでの変わらぬ優しさに思いを馳せながら、彼と過ごす時間の大切さを再認識した。
達也は悦子の気持ちに気づかず、ただ悦子が用意してくれる居心地の良い空間と美味しい料理を心から楽しんでいるだけだった。
悦子の心の中では、達也に対する自分の感情をどうにかして抑え込み、このまま彼との時間を大切にしたいという思いが渦巻いていた。
彼女はこの禁断の感情を誰にも打ち明けることができず、ただ一人でその葛藤と向き合っていた。悦子は、達也が自分をどう思っているかではなく、彼がそばにいてくれること自体が幸せだと感じていた。
その幸せが永遠に続くことはないと知りながらも、悦子はこの瞬間を大切にしたいと願ってやまなかった。
「達也、いつもありがとう。またね」
と悦子は静かに言った。
達也は「悦子さんのおかげで、いつも元気をもらってるよ。また来るね」
と返答し、彼のその言葉が悦子の心を温かくした。
二人の間には、悦子の一方的な感情があることを達也は知らず、悦子はその事実を受け入れつつ、達也との関係をこれからも大切にしていくことを心に決めた。